試験までの学習計画を立て、計画通りに勉強を進めながら毎日の勉強が習慣化されるように、毎日少しでも勉強時間を作るように心がけました。
実はFPの勉強で出てくる言葉や単語って、意外と聞きなれないものも多くて、慣れるまでは結構苦労しました。例えば、普段の生活では「健康保険」を利用する際、保険証を片手に病院に行ったりしますよね。その健康保険にも「健康保険」と「国民健康保険」があったり、「被保険者」「被扶養者」のように、保険や扶養の対象となる人のことを「被」〇〇者と呼んだり、所得や控除といったあまり使い慣れない単語や言い回しなどなど。ですが、知らない単語や言葉は覚えるしかないので、反復したり声に出したりしてしっかり覚えるようにしました。FPの勉強を始めたことで、普段の生活の中で関わる出来事に対して、自分が如何に無知だったかを思い知らされましたが、だからこそ興味を持って取り組めたのも事実でした。ですので、自身の生活を今から少しでも豊かにするためにも、FPの勉強を始めてみて良かったと思えました。
さて、FPの勉強を始めて1ヵ月ほどが経ち、ようやく日々の勉強が習慣化されはじめた頃に、一つの大きな壁にぶち当たることになりました。(実はこの壁があることは分かっていたのですが・・・)

分かっていたのなら、予め回避することはできなかったの?
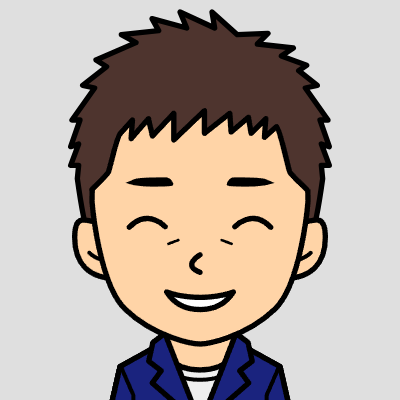
これがある意味、FP2級とFP3級の「壁」だったのかも知れません。
ここで改めて、FP2級がどのようなものなのかを整理してみたいと思います。
資格名称:2級ファイナンシャル・プランニング技能士
実施団体:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会)
社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)
試験時期:1月/5月/9月(年3回)
試験内容:学科試験・・・120分/60問、マークシート式(4択)
実技試験※・・・90分/40問、記述式・選択式
※日本FP協会ときんざいでは、実技試験の実施内容が異なります。
受験料:学科試験・・・5,700円 実技試験・・・6,000円
以前にも記載した通り、FP2級試験の概要は上記の通りですが、実はFP2級には受験資格があります。
ちなみにFP3級試験は、FP業務に従事している、または従事しようとしている人なら誰でも受験することができます。
①AFP認定研修の受講を終了
②FP3級試験の合格
③ファイナンシャルプランナーの実務経験が2年以上ある
④厚生労働省認定金融生涯技能審査3級に合格
上記のいずれかに該当する必要があります。
さて、ここで初めて出てきた言葉で「AFP」というものがあります。実はこのAFPは2級FP技能士と並ぶFP資格の一つなのですが、FP1級と同等のものは、「CFP」と呼ばれています。
簡単に言うと、FP技能士は国家資格、AFPやCFPは日本FP協会が主催する民間資格となります。
| 国家資格 | 民間資格(日本FP協会) |
| 1級FP技能士 | CFP(サーティファイドファイナンシャルプランナー) |
| 2級FP技能士 | AFP(アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー) |
| 3級FP |
ここで上記のFP2級受験資格を確認すると、50歳で初めてFPの勉強を始め、しかも2級からチャレンジしている私が受験資格を有するには、「①AFP認定研修の受講を終了」をクリアする必要があります。
これこそが、前述の「大きな壁」となったわけです。
つまり、私が3ヵ月後のFP2級試験で合格するためには、「①AFP認定研修の受講を終了」した上で、試験の合格基準を満たす必要があったのです。
ではこのAFP認定研修はどのように受講できるかというと、その名の通り、日本FP協会が認定した研修を受講すれば良いのですが、この認定研修をカリキュラムに組み込んだ通信教育が幾つかあったのです。私は前の記事で記載した通り、学習方法としてフォーサイトの通信教育を選んだのですが、私が選んだ講座には、このAFP認定研修も含まれていました。
・FPK研修センター
・大原学園(資格の大原)
・神奈川ファイナンシャルプランナーズ共同組合
・TAC(資格の学校TAC)
・フォーサイト
・ユーキャン

このフォーサイトで受講できる認定研修が大きな壁ってわけですね。
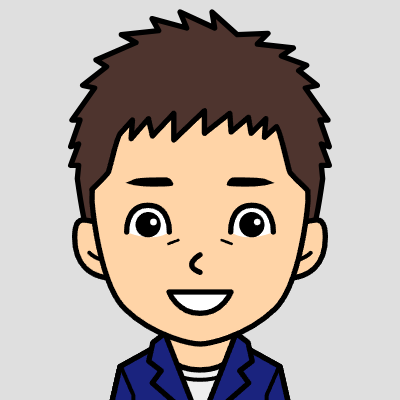
はい。FPの勉強と並行してこの認定研修に合格する必要がありました。
認定研修対象講座を受講-修了すること。
<修了条件>
提案書※の作成・提出、基準点のクリア (’25年1月受験には’24年11月が提出期限)
※提案書・・ファイナンシャルプランナーがお客様の希望するライフプランに合わせて、問題点の指摘や改善提案を行うための書類。
上記の通り、FP2級試験を受けるためには、認定研修対象講座を受講・修了し、課題として提示される架空のお客様の希望するライフプランに合わせた提案書を作成し、期限までに提出、基準点をクリアする必要がありました。そしてこの提案書を作成するためには、ある程度、全体的なFPの知識を理解する必要があるため、計画した勉強とは別に、この提案書作成にかかる勉強もする必要があり、結果的に当初に立てた計画を大きく見直さざるを得なくなってしまうのでした。

スケジュールが遅れちゃったら挽回も大変だー
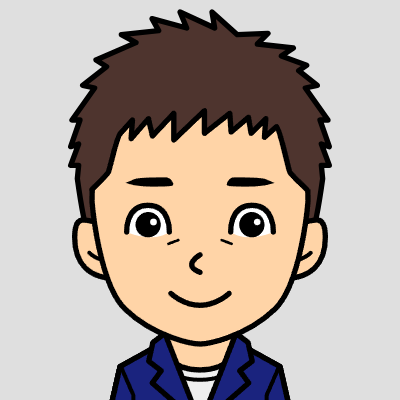
個人的には、このタイミングでの提案書作りはむしろ良かったと思っています。
結果的には、この提案書作成に多くの時間を費やしてしまった訳ですが、私としては、むしろ資格取得後の実践練習ができたような気持ちになり、FPの面白さと奥深さを再確認するとともに、全体感を把握する上でも、色々なことを考えられる良い機会になったと感じています。合わせて提案書を提出した後に、フォーサイト側で採点が行われますが、基準点をクリアすれば、「合格」の連絡があるため、この合格を実体験できるという意味でも、この認定研修をクリアできたことが大きな自信と励みになりました。
そして、提案書を提出した後に、改めてスケジュール遅延を考慮した形で、再度フォーサイトアプリのスケジューリング機能を使い、試験日までの計画を立てることができました。
新しいスケジュールを見ながら、まだまだ間に合う!絶対に合格できる!と信じて、改めて勉強を進めることになりました。

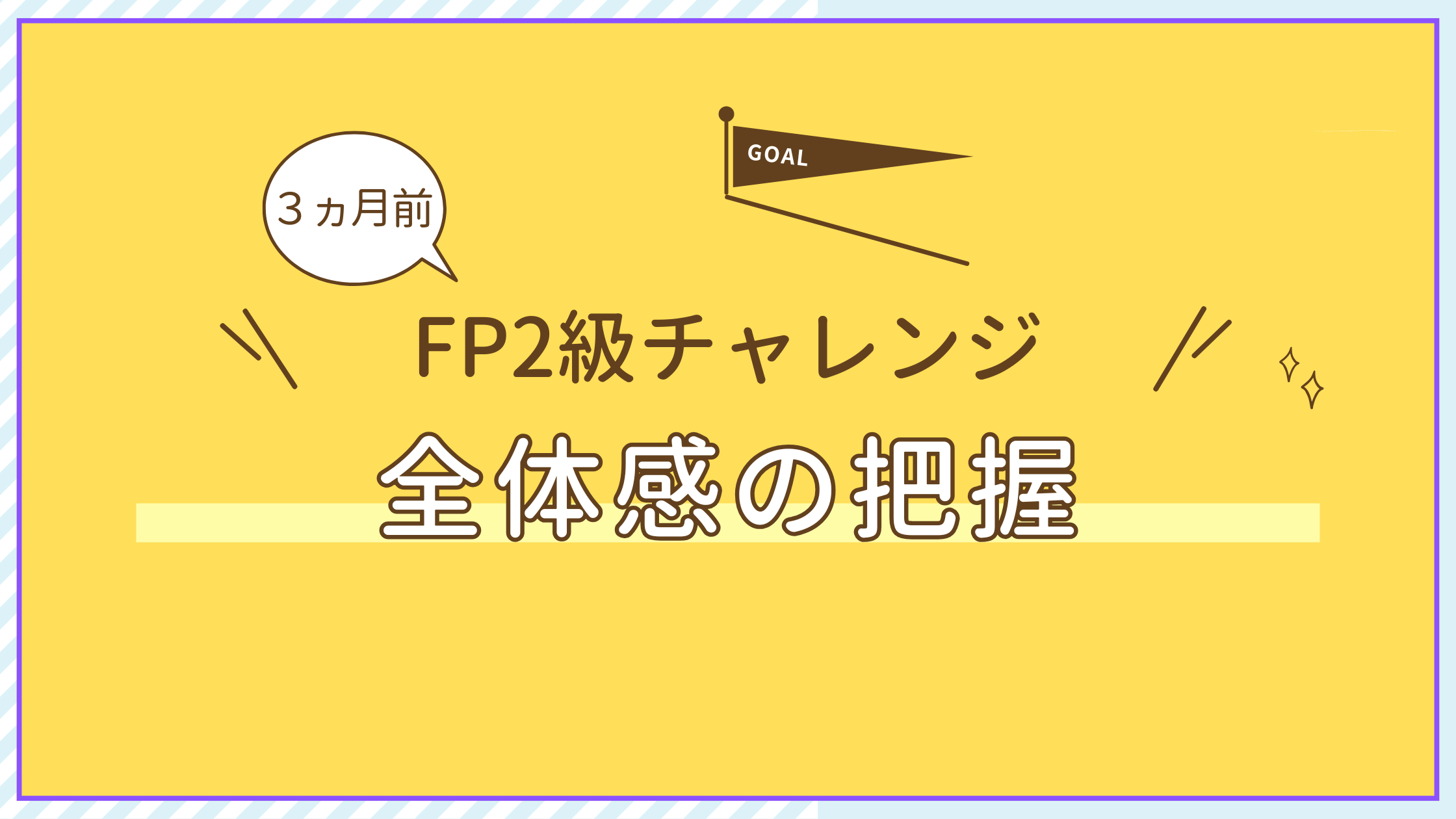


コメント