FPは顧客との信頼関係の上に成り立つ仕事ですので、高い職業倫理が求められ、それに応えていかなければなりません。FPの守るべきルール、またはモラルとして「顧客利益優先」「秘密の保持」などがあげられ、コンプライアンスの徹底が求められます。FPは顧客の個人的な情報を知り得る立場にありますので、情報管理は徹底しなければなりません。
また、FPがファイナンシャル・プランニングを行うにあたっては、様々な領域に関わることになり、弁護士、税理士、保険・金融・不動産などの専門家の協力も必要となりますので、それぞれの領域に関わる関連法規を遵守する必要があります。
ファイナンシャル・プランニングと関連法規
実は私もFPの勉強を始めてから知ったのですが、FPには、FPの業務を規定する法規制がありません。しかしFPの業務は、法律や税務、保険分野など様々な領域に関わりますが、弁護士や税理士、保険募集人など、資格をもった専門家しか行うことができない業務があるため、それらを規定する法規制に抵触しないように注意する必要があります。

FP業法とか、ないのですか??
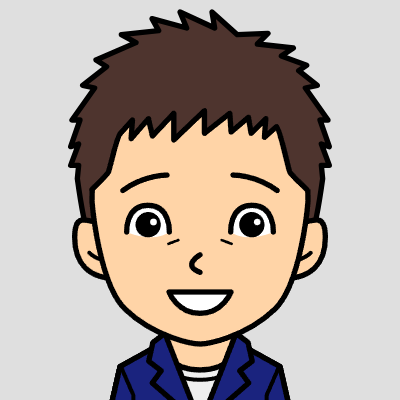
残念ながら規定されていないのです。
FPと関連する業務の法規制には以下があります。
それぞれの法規制に抵触しないように注意する必要があります。
弁護士の資格を持たないFPは、具体的な法律相談や法律事務の提供を行ってはいけません。
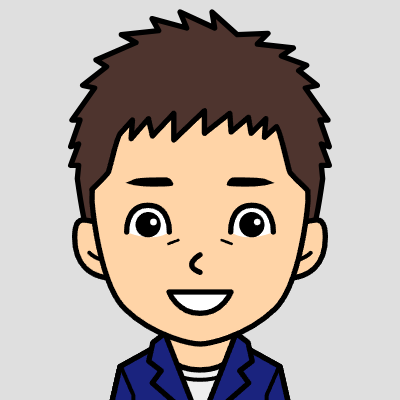
弁護士の資格を持たないFPが法律や相続・遺産に関する一般的な説明をするのは問題ありません。
税理士資格を持たないFPは、具体的な税務相談や税務書類の作成を代行してはいけません。
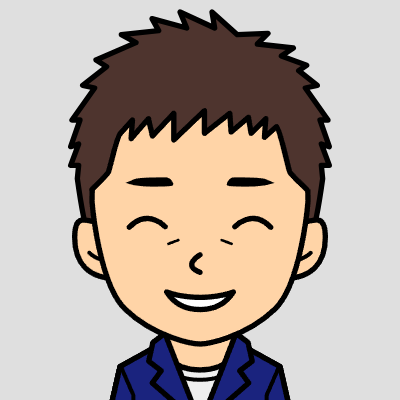
有償/無償に関わらず、税務相談や書類作成代行を行ってはいけません。
金融商品取引業者としての登録を受けていないFPは、具体的な投資の助言や顧客の資産運用を行うことはできません。
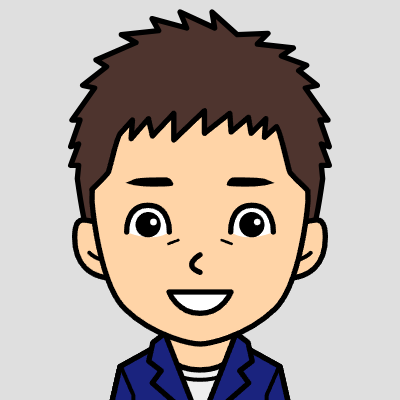
具体的な金融商品の銘柄を勧めることもできません。
保険募集人の資格を持たないFPは、保険の募集および、勧誘を行ってはならない。
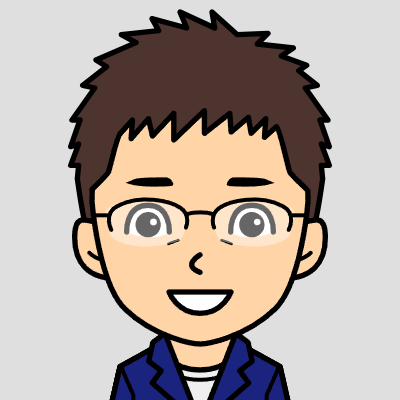
具体的な保険商品を勧めることもダメなのです。
社会保険労務士資格を持たないFPは、年金事務所や労働基準監督署への申請書類の作成や手続きの代行作業を行ってはならない。
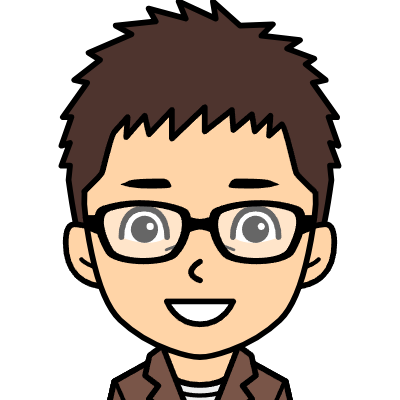
社会保険労務士の独占業務をFPが行うことはできません。
上記のように、それぞれの分野では、法規制で定められた範囲で業務を行うことができますが、FPにとっては、色々と制限があるのも事実です。ですから、FPは様々な分野の専門家と連携し、顧客の課題を解決していく必要があります。もしくは、FP自らそれぞれの専門分野の資格を得ることで、より専門的な業務も行うことができます。FPはお金に関わる幅広い知識を生かしつつ、必要な専門家と連携する、或いは自らその分野の専門家になることで、顧客の課題に応えることができる面白い職業にもなり得ると思います。
例題にチャレンジ
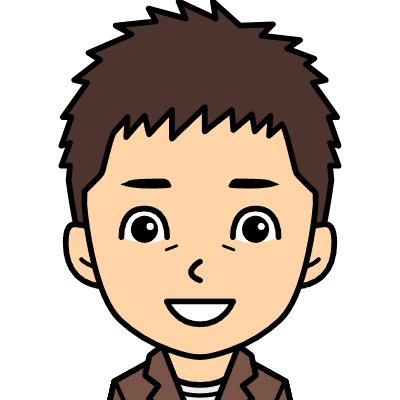
それでは最後に例題を解いてみましょう。
①ファイナンシャル・プランナーは、他の専門家と協同して顧客の要求に応えていくというコーディネート能力が必要とされ、他の専門家との関係を構築し、いつでも仕事ができる体制をつくっておくことも大切である。(〇/×)
②生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の一般的な商品性について説明することは、保険業法において禁止されている。(〇/×)
③弁護士や司法書士の資格を持たないファイナンシャル・プランナーが、顧客から依頼を受け、事件性のある債務整理の相談に応じる行為は、有償か無償を問わず適切な行為である。(〇/×)
④税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、所得税の確定申告を自ら作成する顧客に対して、国税庁のホームページを紹介し、インターネットによる電子申告を勧める行為は適切である。(〇/×)
⑤ファイナンシャル・プランナーがライフプランニング業務を行う場合の職務上の原則は、顧客の利益最優先、守秘義務の遵守の2つを徹底することで十分である。(〇/×)

学科試験で問われるような問題ですね。
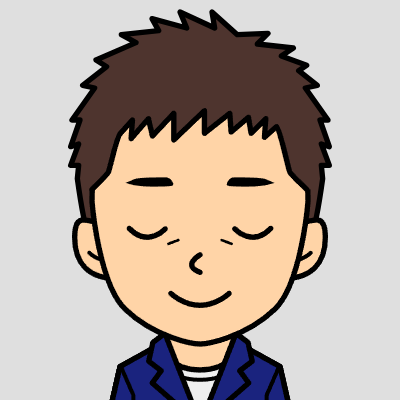
学科試験では問題を解く速さと正確さが必要になります。
①〇 ②× ③× ④〇 ⑤×

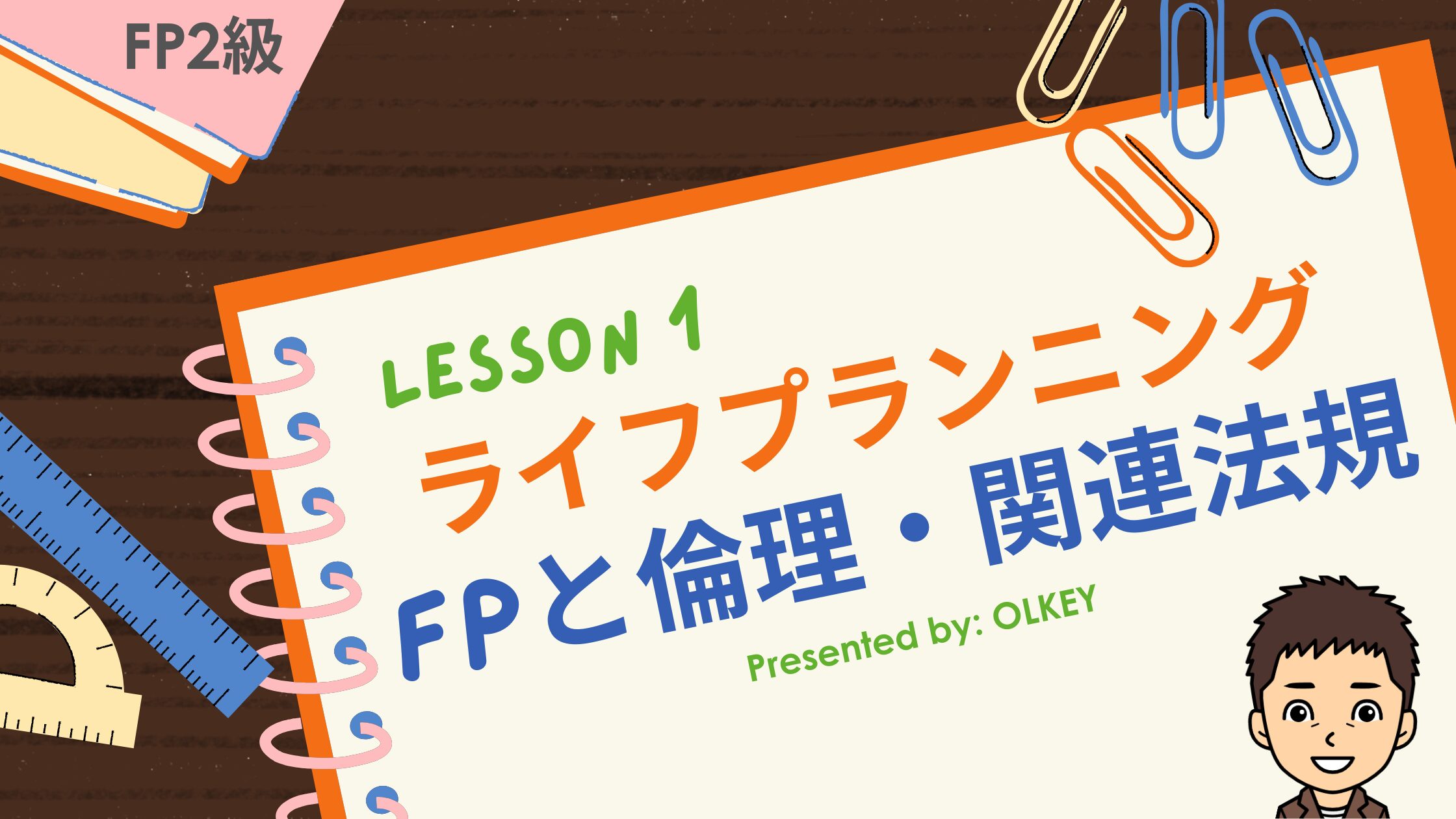


コメント